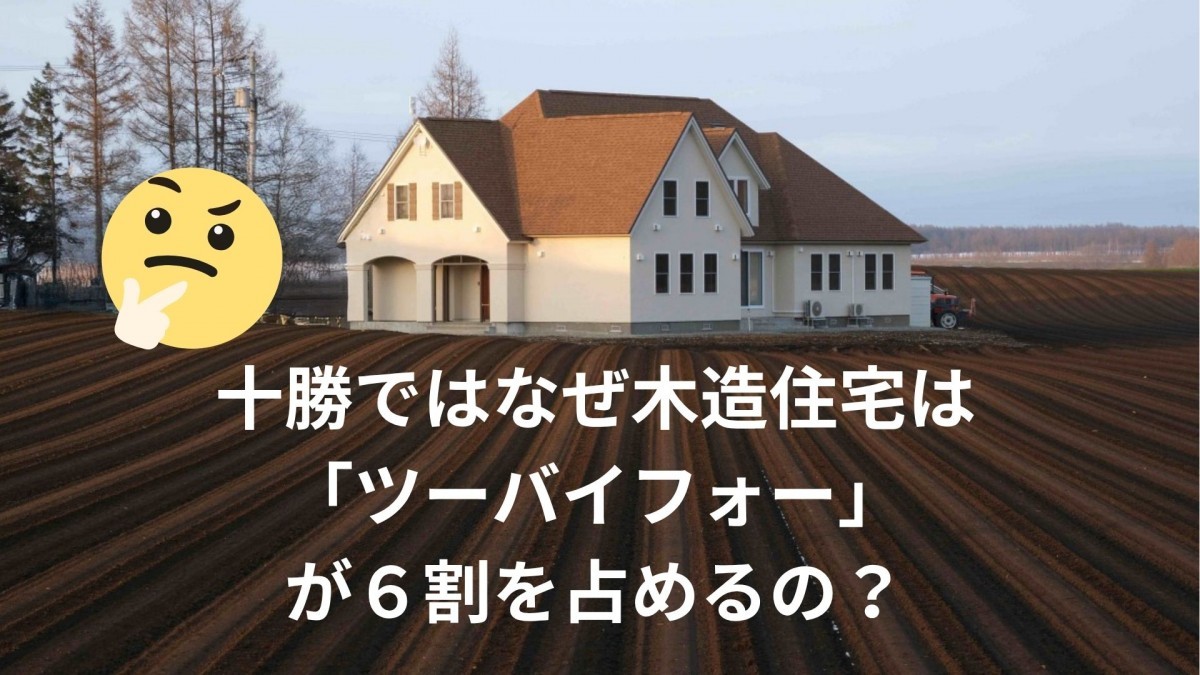
今回は、当社にとって、とても大切な「ツーバイフォー」について語ります。
十勝の先輩工務店が作り上げたツーバイフォーの歴史
日本の木造住宅は、在来工法が約8割、約2割がツーバイフォー工法(正式名称は枠組壁工法)で建てられています。

ところが、十勝では約6割がツーバイフォー工法で建てられています。日本国内でも類をみないほどツーバイフォーが盛んな地域なのです。
十勝でツーバイフォーが盛んになったきっかけは、1975年に、十勝の工務店、建材店の先輩たちがアメリカの家づくりを視察したのがきっかけです。
カナダやアメリカでは、木造住宅の約9割がツーバイフォーで建てられています。北米の厳しい寒さ、暑さから身を守るために断熱・気密・耐震性能に優れた住宅が必要だったこと、そして作業効率が良く工期が短い、品質が安定するというメリットがあるためです。
帰国後の1979年に十勝2×4協会が発足。赤坂建設さん、久保工務店さん、岡本建設さん、ウッズ建築設計事務所さんなど十勝の地場企業が技術の研究とレベルアップ、そして広報活動などに奮闘された結果、国内でも類を見ないほど、十勝でツーバイフォーが普及するようになりました。
技術、ノウハウを共有しあえる十勝2×4協会
私(朝日良昌)が20代で就職した帯広のゼネコンもツーバイフォーを採用していました。またその後入社した工務店は十勝2×4協会会員で、私も活動に参加させていただくようになりました。
十勝2×4協会では、会員が、最低年1回は、フレーミングの完了した現場で、2×4工法の基準に沿って、釘の打ち方やピッチ、枠組材、専用金物による緊結などをチェックする「フレーミング検定」を受けます。それとは別に、年に1回、気密測定も義務付けられています。

こうした現場でのチェックだけでなく、月1回の定例会も開催されていて、そこでは各社が日頃取り組んでいる設計施工などの家づくり全般、さらには経営、広報に至るまで、お互いにノウハウを開示し、他社の取り組みであっても遠慮なく意見を出しあっています。
十勝2×4協会の正会員は、十勝で家づくりをしている工務店たちです。同業者なので、競合することも多々あります。にもかかわらず、お互いの施工現場を公開し、技術や知識を共有したり、それぞれの会社が抱える課題を相談し、遠慮なく指摘します。こうした同業者の団体としては、これほどオープンに刺激しあえるというのは非常に珍しいことではないかと思います。
ツーバイフォーの強み
ツーバイフォー住宅の壁や床、屋根は、2×4材や2×10材等の木材を組んで「枠組」をつくり、「枠組」に構造用面材を接合し、剛性の高い版(「ダイヤフラム」)を構成、それらを一体化して頑強な「六面体構造」を形成します。
また、構造材やくぎ・金物のサイズ・使用方法・使用箇所から施工の手順まできめ細かくマニュアル化されています。

このように、断熱・気密・耐震・耐火などを確保しやすい構造、そしてルールがきめ細かく明確に定められているので、大工さんや職人さんの技量に左右されにくく、安定した住宅性能を確保できるというのが一番の強みだと思います。

参照:好きな家具×雑貨が似合う「古民家」の世界観/芽室町Kさん
一方、設計面やリフォームなどの際に、在来工法に比べ自由度が少ないと言われることもありますが、それは品質・性能を確保するためのルールが明確なので、それに反することはできないということでもあり、安心して暮らせる、家族を守れる家づくりになるということでもあります。また、当社の施工例を見ていただけるとわかるように、お客様の要望を柔軟に叶える家づくりができますので安心してご相談いただければと思います。https://co-vill.com/works/
2025年 十勝2×4協会会長に就任
十勝2×4協会の会員としてさまざまな活動に参加するようになって15年ほど経ちます。当初は、先輩たちから、自分が施工管理する現場のチェックを受け、厳しい指摘をいただくこともありました。逆に他社の現場を拝見し、優れた技術やこだわりを学んだり、成長の機会にもなりました。
2019年から6年間は副会長、2025年には会長を拝命いたしました。今まで一部の幹部に頼っていた部分などを広く会員が力をあわせて運営できるように、年12回の定例会のテーマや内容を、技術・省エネ部会や、気密部会など、各部会にお任せしたり、若手の提案を会の発展につなげていくような取り組みも始めました。

十勝2×4協会は、2028年に50周年を迎えます。協会の活動を賛助会員を含め多くの人に「見える化」したり、コロナ禍に活動が減ってしまったイベント、広報活動などの強化など、将来に向けた取り組みも進めていきたいと思っています。
先輩工務店の方々が作り上げてきた十勝のツーバイフォーの実績を大切にしながら、法制度や顧客のニーズの変化、大工の担い手不足など、新たな課題に対しても連携しながら取り組んでいける組織にしていきたいと思っています。